三つ編み

住む国も環境も違う三人の女性が、それぞれの困難に立ち向かっていく姿が描かれる。出会うことはない三人だけれど、懸命に生きることが他の女性を支えることになるラストが嬉しい。すべての女性へのエール!

本が好き! 1級
書評数:60 件
得票数:603 票
ジャンルは小説、エッセイ、時に児童文学かな。おばさんは目が弱くなってきてたくさん読めなくなってきました。読むのも書くのもぼちぼちと。

住む国も環境も違う三人の女性が、それぞれの困難に立ち向かっていく姿が描かれる。出会うことはない三人だけれど、懸命に生きることが他の女性を支えることになるラストが嬉しい。すべての女性へのエール!





ソマリに片思い中の著者、高野さん。ソマリ人の家庭料理見たさに秘境「キッチン」に潜入?氏族社会の選挙事情や南部ソマリアの戦闘、北部と南部の違いなど、行った人にしか書けない魅力にあふれています。





紛争地域で国際NGOとして活動してきた著者が、14歳の読者を想定して、紛争の背景や人道支援の矛盾、国連の限界、平和の構築などについてわかりやすく説明している。頭の固い大人こそが読むべきかもしれない。





「まほろシリーズ」は、面白い。多田にも行天にも複雑な過去があるけれど、どたばたな日常の中にも「前に進む一歩」が必要なことがあって、二人でいるからそれができるのだろう。映像も小説も両方いいのは珍しい。





ミレニアム3部作の最終巻。サスペンスの面白さは言うまでもないが、幼い時から孤独な闘いをしてきたリスベットが、信頼できる人々に巡り合って、徐々に心を開き成長していく様子が素晴らしい。読後感が爽やか。





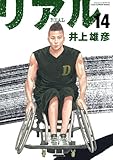
動き出した高橋!黙々と基礎的な練習をする高橋と、野宮・清春の人生が交差する日が楽しみだ。わき役陣がそれぞれの人生をリアルに生きているのにも唸る。ヤマの再登場が嬉しかった。1年半後の発売まで待てないよ。






「自分が何かの終末に居合わせることになるなどと、人は考えもしない。」世界の最果て極北の地で、終末と向き合いながら生きるとしたら・・。主人公の名は「メイクピース」
こういうのは「近未来小説」というのだろうか。 だが、小説の中で起こることは、 今現在、世界中で進…





「発達障害」と診断されるケースが急増しているという。だが、実際は「愛着障害」でも似たような症状を呈するのだと筆者は指摘する。
「発達障害」は、本来生物学的要因によるものとされる。 つまり、脳機能の障害であると。 だが、…





5人の親密な友人の中で「つくる」だけ色がない。自分が空っぽな存在に思える時って、誰にでもあるような気がする。自分が前に進むために。彼の巡礼の年。
この作品の情報が流れた時、 筆者の昔のエッセイを思い出した。 高校生の時、差別のことを全く知らず…






アフリカの「ソマリア」という国について何か知っていることがあるだろうか。内戦が続いている。飢餓に苦しんでいる。近海には海賊が出没する。・・それを疑ってみたことは?
内戦が続いているソマリアからの情報は少ない。 ソマリアに「ソマリランド」なるものがあることを、 …





むむむ、高知県に行きたくなってきてしまった。みごとに有川さんの術中にはまっている。最初はダメダメな「おもてなし課」が成長して行く物語に、2組の恋愛模様が程よく絡んでいくのはさすが。






人が暮らしていくこと、生きていくことって、こういう丁寧な仕事の積み重ねなんだなって思う。この繊細な絵もお話の雰囲気にぴったり。






子どもの時こんな伝記を読んだらどんなにワクワクしただろう。万次郎は何でも知りたがり、どんどん新しいことを吸収していく。困難を抱えながらも万次郎を養子に迎えるホイットフィールド船長も魅力的だ。




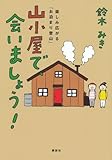
体力にも自信がないし「山小屋」の経験もないので、山小屋に泊まるのはちょっと敬遠していたけど、これを読むと、山好きの人たちと一緒に山小屋に泊まって、山の夜や朝を感じてみたい気がする。





副題に「読み書きが困難な学習障害の息子と母の成長物語」とある。臨床心理学博士の筆者は、専門家としてではなくむしろ母親としての心情を綴っているように感じる。障害を持つ息子も自ら本音を語っている。
ディスレクシアとは、読み書きが困難な学習障害のことを言う。 著者の息子デーヴィッドはディスレクシア…
![]()




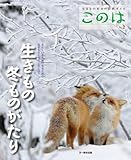
豊富なカラー写真と丁寧な解説で、冬の自然観察がより楽しくなる一冊。雪の野原に出かけたくなります。
久々の当選です!献本ありがとうございました。 表紙の雪の中の子ギツネがキュート! 最初から心を奪われ…





赤ん坊を抱えて孤立無援の珊瑚の目に入ったのは「赤ちゃん、お預かりします」の小さな張り紙だった。焼きたてのパンの香りや温かいスープの湯気が漂ってきそうな物語。人との出会いによって雪と珊瑚の世界は広がる。
自分も、ごく若い時は「自立する」というのは、 自分一人で何でもできることだと思っていた。 だが、…
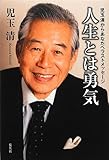
2011年、惜しまれながら亡くなった児玉清さんのインタビューとエッセイが収められている。ロマンティストで熱血漢で礼儀正しい児玉さんが生き生きとよみがえる。疎開した時の祈りの体験が心を揺さぶる。

「人が集えば必ず生まれる序列に区別、差別にいじめ。」確かにそうだ。どんないい人でも必ず「人を下に見る」ということがある。バブル世代の筆者の成長に沿って書かれており、面白い世代論にもなっている。

自分は理系の人に憧れがある。でもこの本はけっこう自虐的に書いてるかも。時々大笑いするところもあるけれど、理系・文系の違いじゃなくて器用・不器用の違いもあるかなあ。