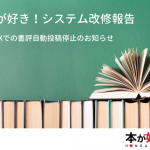hackerさん
レビュアー:
▼
「これが真実だ!仕事がねぇ...力がねぇ!これが真実だ!身の置き場...身の置き場がねぇ!のたれ死にでもするほかねぇ...これがその真実だ!(中略)そんなものがおれにとって何になる」(登場人物の台詞)
文学に限らず、どんな芸術でも、現在の自分が評価し判断するしかないわけですが、古典と呼ばれる作品に関しては、それが世に出た時の社会状況なり、その後の芸術の発展を鑑みての位置づけなりからの視点は、やはり必要だと思っています。
本書は、マキシム・ゴーリキー(1868-1936)が、1902年に発表した二作目の戯曲であり、彼の最も有名な作品でしょう。この作品を生んだ作者の生い立ちについて、訳者中村白葉は本書解説で次のように述べています。
「彼(ゴーリキー)は、まだ十歳にもならないうちから、家計を助けるために町のくず拾いとなり、間もなく家をはなれて靴屋の小僧を振りだしに、製図屋の徒弟、ウォルガがよいの船のコックの見習い、聖像絵師の下職、パン工場の職人、荷揚げ人足、番人、放浪者等々、わずか数年の間にじつに目まぐるしいばかりの境遇の転換を行った(中略)学校教育といっては、わずかに5か月小学校に通ったきりで、その後はほとんど、幼年時代からはやくも『人々の中へ』出て、自分自身の労働によってからくも口を糊して来たような、悲惨きわまる境遇にあった」
こういう人生経験が、正に社会の「どん底」に生きる人々を描いた本書に活かされていることは、疑いないでしょう。
しかし、今回久しぶりに再読して思うのは、20世紀初めに、こういう集団劇を書いた意義は大きかったということです。例によって、ものすごく話が飛躍しますが、『ウエストサイド物語』(1961年)のミュージカル映画史における位置づけを連想します。つまり、『ウエストサイド物語』より前のミュージカル映画は、基本的に個人の芸を見せることが中心であり、フレッド・アステアとジンジャー・ロジャースのコンビの踊りが中心に据えられていた『コンチネンタル』(1934年)から『カッスル夫婦』(1939年)に至る作品群は、その典型です。しかし、『ウエストサイド物語』以降ミュージカル映画には集団劇の要素がずっと強くなりました。実は、私個人としては『ウエストサイド物語』は嫌いなのですが、その歴史的意義についてまで、否定するつもりはありません。
本書に、後に社会主義リアリズムの始祖として、スターリンに祭り上げられることになるゴーリキーの、20世紀初頭としては極めて異例の集団劇という地位を与えることは、間違いではないと思います。本書の最大の特徴は、目立つ目立たないはあっても、主人公と呼べる登場人物が存在しないことで、それゆえ、生身の人間が演じる舞台と違い、文章だけ読んでいると、誰が誰だか混乱するような感じもあって、登場人物一覧は必須なのですが、これも「名もなき人々」ばかり登場する作品には相応しいことです。こう考えると、エイゼンシュテインの傑作『戦艦ポチョムキン』(1925年)が素人ばかり出演する集団劇だったことも、本書が頭にあったのだろうと思います。
また、罵倒文学の誕生を世界に宣言した、20世紀文学の金字塔であるセリーヌの『夜の果てへの旅』(1932年)にも、本書の罵詈雑言が飛び交う台詞が、影響を与えていた可能性はあるでしょう。
さらに、この作品は、明らかに、当時の上流階級の人たちが観客になることを想定していません。これも、当時としては、異例だったのではないかと推測します。
ただ、念のために付け加えると、これらの要素は、大衆演劇の世界では昔からあったのだろうとも思います。ですから、ゴーリキーが創造したというわけではないでしょう。そうは言っても、それらをとりまとめ、一つの文学作品に仕立て上げたこと、そしてそれが後世に与えた影響を考えると、やはり本書は後世に、そしてこれからも語り継がれるべき作品です。
また、本書で描かれている、社会の「どん底」の人々の姿、残念ながら、これが現在に至るまで世界的普遍性を持って、我々にうったえていることは、言うまでもないでしょう。
本書は、マキシム・ゴーリキー(1868-1936)が、1902年に発表した二作目の戯曲であり、彼の最も有名な作品でしょう。この作品を生んだ作者の生い立ちについて、訳者中村白葉は本書解説で次のように述べています。
「彼(ゴーリキー)は、まだ十歳にもならないうちから、家計を助けるために町のくず拾いとなり、間もなく家をはなれて靴屋の小僧を振りだしに、製図屋の徒弟、ウォルガがよいの船のコックの見習い、聖像絵師の下職、パン工場の職人、荷揚げ人足、番人、放浪者等々、わずか数年の間にじつに目まぐるしいばかりの境遇の転換を行った(中略)学校教育といっては、わずかに5か月小学校に通ったきりで、その後はほとんど、幼年時代からはやくも『人々の中へ』出て、自分自身の労働によってからくも口を糊して来たような、悲惨きわまる境遇にあった」
こういう人生経験が、正に社会の「どん底」に生きる人々を描いた本書に活かされていることは、疑いないでしょう。
しかし、今回久しぶりに再読して思うのは、20世紀初めに、こういう集団劇を書いた意義は大きかったということです。例によって、ものすごく話が飛躍しますが、『ウエストサイド物語』(1961年)のミュージカル映画史における位置づけを連想します。つまり、『ウエストサイド物語』より前のミュージカル映画は、基本的に個人の芸を見せることが中心であり、フレッド・アステアとジンジャー・ロジャースのコンビの踊りが中心に据えられていた『コンチネンタル』(1934年)から『カッスル夫婦』(1939年)に至る作品群は、その典型です。しかし、『ウエストサイド物語』以降ミュージカル映画には集団劇の要素がずっと強くなりました。実は、私個人としては『ウエストサイド物語』は嫌いなのですが、その歴史的意義についてまで、否定するつもりはありません。
本書に、後に社会主義リアリズムの始祖として、スターリンに祭り上げられることになるゴーリキーの、20世紀初頭としては極めて異例の集団劇という地位を与えることは、間違いではないと思います。本書の最大の特徴は、目立つ目立たないはあっても、主人公と呼べる登場人物が存在しないことで、それゆえ、生身の人間が演じる舞台と違い、文章だけ読んでいると、誰が誰だか混乱するような感じもあって、登場人物一覧は必須なのですが、これも「名もなき人々」ばかり登場する作品には相応しいことです。こう考えると、エイゼンシュテインの傑作『戦艦ポチョムキン』(1925年)が素人ばかり出演する集団劇だったことも、本書が頭にあったのだろうと思います。
また、罵倒文学の誕生を世界に宣言した、20世紀文学の金字塔であるセリーヌの『夜の果てへの旅』(1932年)にも、本書の罵詈雑言が飛び交う台詞が、影響を与えていた可能性はあるでしょう。
さらに、この作品は、明らかに、当時の上流階級の人たちが観客になることを想定していません。これも、当時としては、異例だったのではないかと推測します。
ただ、念のために付け加えると、これらの要素は、大衆演劇の世界では昔からあったのだろうとも思います。ですから、ゴーリキーが創造したというわけではないでしょう。そうは言っても、それらをとりまとめ、一つの文学作品に仕立て上げたこと、そしてそれが後世に与えた影響を考えると、やはり本書は後世に、そしてこれからも語り継がれるべき作品です。
また、本書で描かれている、社会の「どん底」の人々の姿、残念ながら、これが現在に至るまで世界的普遍性を持って、我々にうったえていることは、言うまでもないでしょう。
お気に入り度:









掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
「本職」は、本というより映画です。
本を読んでいても、映画好きの視点から、内容を見ていることが多いようです。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:岩波書店
- ページ数:174
- ISBN:9784003262726
- 発売日:1979年01月01日
- 価格:525円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。